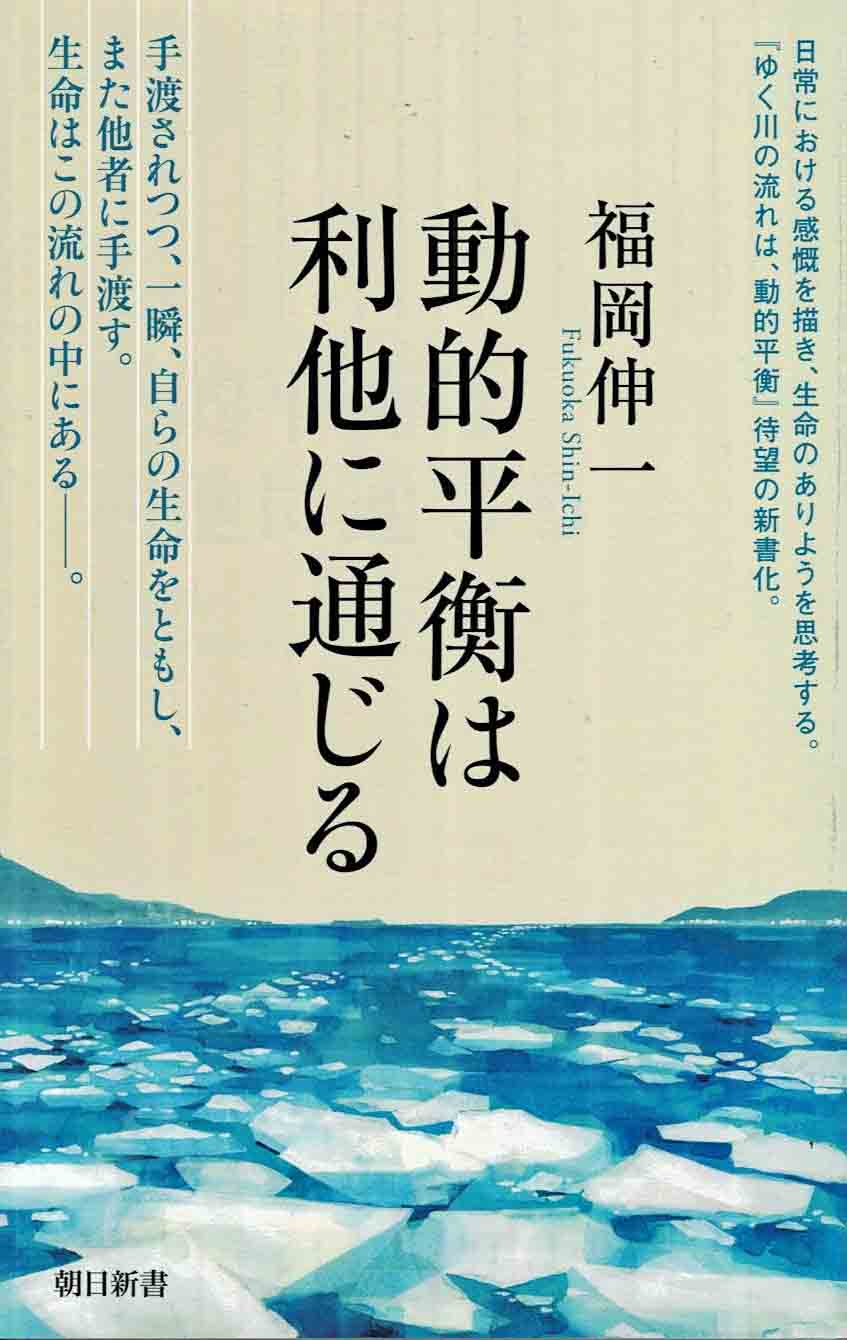
「動的平衡」について、著者・福岡伸一さんは、私の生命論のキーワードであるという。鴨長明の『方丈記』の冒頭ほど、みごとに生命の動的平衡を言い表した文章を知らないと。ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず、よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとどまりたるためしなし ……みごとに動的平衡の生命論を歌い上げている。
生命とは何かとの問いに対して、細胞からなるもの、DNAを持つもの、呼吸しているもの、代謝しているもの、増殖するもの等々の答があるだろう。いずれの答えも、生命の本質には到達できない。生命の特性を外部から列記しているだけだからだ。生命の内部から生命のあり方を捉える必要がある。行き着いたのが「動的平衡」の概念だ。
「動的平衡」は新陳代謝ではない。新陳代謝では古いものが捨てられ、新しいものが作られるだけ。「動的平衡」は,新しいものでも積極的に壊す意味があるとする。秩序はそれが守られるためにまず壊される。システムが変わらないために変わり続けること。生命の営みは、分解と合成という相反することを同時に行い、しかも分解を先回りして行うこと。これを「動的平衡」と呼ぶことにしたのだ。
生命は環境から絶えず物質を取り入れている。植物では炭酸同化作用として、太陽のエネルギーを固定し虫や鳥に与える。動物は他の生物を食うという形。同時に生命は環境に絶えず物質を供給している。呼吸や排泄、あるいは食べられるという形だ。生命は本質的に利他的であること。手渡されつつ、手渡す。利他性によって、すべての生命はは地球の上に共存しているのだ。「動的平衡」とはこの営みを指す言葉でもある。
生命を形作る生体物質はたんぱく質にせよ、DNAにせよ、あらかじめ分解されることを予定して作られている。分解されたあと、他の生命体によって再利用されることが予定されて作られている。たんぱく質を構成するアミノ酸はまた他の生命体に手渡されて新たなたんぱく質になる。進化は決して利己的遺伝子の独壇場ではなく、利他的共生が織りなしたものである。
宇宙の大原則に「エントロピー増大の法則」がある。物質(非生命体)は、この法則に身を任せざるを得ない。秩序あるものは無秩序になる方向にしか変化しない。形あるものは崩れ、濃度が高いものは拡散し、高温のものは冷え、金属はさびる。
生化学者シェーンハイマーは生命が絶えず自らを分解しながら作りなおしていることを明らかにした。言い直せば、「生命は、エントロピー(乱雑さ)増大の法則にあらがっている」と。生命は、自ら壊すことによって,細胞が内部に無秩序が広がることを回避している。絶えず前もって故障の芽を摘んでいるのだ。変わらないために、変わり続ける。壊すことは作ることよりも実は創造的なのである。
21世紀になると別の側面がクローズアップされた。生命が壊すことを一生懸命にやる事実に、何通りもの方法で休みなく行っていることだ。細胞内にプロテアソームやオートファジーと呼ばれる分解システムが発見されたのである。休みなくタンパク質や細胞内の構造体が壊されている。細胞自身もアポトーシスという自殺プログラムによって躊躇なく自壊し、交換されている。分解と合成の動的な平衡こそが生きているということである。
生命を構成するあらゆる物質は絶え間のない動的平衡の中にある。だったら、記憶などたちまち失われてしまうのではないか、との疑問がある。まず、記憶は物質ではない、ということ。脳細胞と脳細胞のあいだにある。シナプスで連結されてできた脳細胞の回路に電気が通るたびに「生成」されるのが記憶である。
記憶のメカニズムの理解には、山手線をイメージしてみよう。路線の開始当時のレールや枕木は今や姿もかたちもない。絶えず交換や補修が行われ、すっかり様変わりしている。しかし渋谷の次は原宿で原宿の次は代々木でその次は新宿という路線図はずっと同じままである。脳の神経細胞の成分は、山手線のレールや枕木にあたる。それらは絶えず更新されるが、神経細胞と神経細胞のつながり方自体――つまり駅と駅の関係は保たれる。その回路に電気が流れたとき、同じ記憶がよみがえる。記憶は物質として保持されるのではなく、関係性として保持されているのである。
◆ 『動的平衡は利他に通じる』 福岡伸一、朝日選書、2025/4