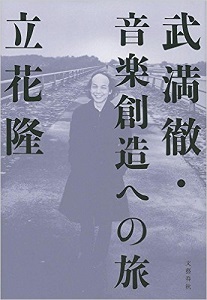
武満作品には、かねて何回か実演には接しているのだが、なかなか熱心なファンにはなれなかった。どうも、個人的な音楽鑑賞能力が、まだまだ武満徹の音楽レベルに追いついていないようである。本書は二段組みで780ページの大冊。ようやく読み終えて、この機会に、武満作品の魅力を再確認したいと思った。(武満徹:1930-1996年没、享年66歳)
本書は立花隆が武満徹への膨大なインタビューをまとめたものだ。興味深いエピソードも満載。音楽を担当した黒澤明の『乱』では激しいトラブルがあったよう。武満は平気でズバズバ意見を言うが、黒澤は面と向かっては文句を言えないタイプ。朝ホテルの部屋のドアの下から、ズズズッと紙が入ってくる。それに「ぼくはきみの音楽が大きらいです。黒澤明」なんて書いてあったそうだ。
デビュー作品はピアノ曲《二つのレント》(1950年)。山根銀二などの音楽評論家から「武満作品は音楽以前である」と酷評されたそうだ。かなり傷ついたという。
国内をさしおいて、武満の名が国際的に知られるようになったのは、《弦楽のためのレクイエム》からである。この曲ははじめ東京交響楽団の定期演奏会で発表された(1957年)。音楽評論家ヒューエル・タークィによって、ストラヴィンスキーに紹介されたことが大きな転機となったそうだ。ストラヴィンスキーは、「この音楽は実にきびしい(インテンス)、全くきびしい。このようなきびしい音楽が、あんな、ひどく小柄な男から、生まれるとは」と評したという(1959年)。この一曲で、武満はたちまち国際的盛名をはせる結果となった。
タークィはもともとサンフランシスコで活躍していた作曲家かつ打楽器奏者。音楽批評もやっていて、アメリカ音楽界ではかなり名前が通っていた。読売交響楽団でティンパニー奏者としてスカウトされ日本にやってきた。「アサヒ・イブニング・ニュース」に音楽批評を書き始め、アメリカに日本の現代音楽の紹介も始める。友人の音楽家に日本の作曲家の譜面を送ったり日米現代音楽の架け橋の役をはたしていた。
小澤征爾は、1960年代前半から各地で武満の作品を演奏し、彼の名を世界に知らしめる大きな力となっていた。《弦楽のためのレクイエム》について、「譜面をもらってびっくりしました。こんなすごい作曲家が日本にいたのか。とにかく音の使い方がこれまでの作曲家とぜんぜんちがう」と。小澤はすぐにアメリカ各地で、《弦楽のためのレクイエム》を取りあげるようになった。武満は国内よりも海外で評価が高い作曲家になっていく。
武満の代表作品である《ノヴェンバー・ステップス》は、琵琶と尺八とオーケストラによる一種の二重協奏曲と言えるだろう。武満の音楽作品で、琵琶が主役に用いられたのは、小林正樹監督『切腹』(1962年)が初めて。琵琶と小編成のオーケストラで革命的な映画音楽を作っていた。映画監督の篠田正浩監督は、「琵琶の一打ちにあんな魄力が秘められているとは……」と。「『ノヴェンバー・ステップス』を聞いたとき『切腹』がよみがえってきた」と言う。
《ノヴェンバー・ステップス》はニューヨーク・フィルの創立125周年記念としての委嘱作品である。ここでも、小澤征爾が当時の音楽監督レナード・バーンスタインに武満作品を紹介したことが委嘱への大きなキッカケとなっている。作曲は小諸近くの山荘に閉じこもって、尺八奏者・横山勝也と琵琶奏者・鶴田錦史を頭において作曲された(1967年)。鶴田はすぐ隣の別荘に移り住み、武満の求めに応じて琵琶のあらゆる奏法を解説し、武満の書いた譜に従って音を出してみせた。
《ノヴェンバー・ステップス》の初演は、1967年11月、ニューヨーク・リンカーン・センターに2人の独奏者を迎えて小澤征爾の指揮で行われた。初演に先立ち、小澤は独奏者とともに、自らの本拠地トロントで数週間にわたるリハーサルを行い万全を期した。いまだかつてない試みでもあり、日本人としてこの曲だけは絶対に失敗できないという背水の陣的な気持ちで、初演に臨んだという。
初演は成功裏に終わったが、いちばんこたえたのは永六輔さんの評だったそうだ。このとき、永はたまたまニューヨークに来ていて、感想をどこかに書いたらしい。「気持ち悪かった」と。着物を着た人が燕尾服を着たオーケストラの前に出てきて、「ベーン」と音を出すのを聞いたら、気持ち悪くて鳥肌が立ったと。自分の音楽をエキゾティシズムで見られるのはたまらないという気持ちを武満は強く持っていた。
武満の意識的なノヴェンバーステップス離れが始まった。次に書いた大きな作品は、《ピアノとオーケストラのためのアステリズム》(1968年)。トロント交響楽団の定期公演で小澤征爾の指揮で初演された。ピアノ独奏は高橋悠治。従来、武満は小さい音が好きで、吉田秀和に『静謐の美学』と言われたことがある。この《アステリズム》は「ぼくの作品のなかでいちばん大きな音がする曲」だという。
先のタークィは武満のユニークさを分析して、「インストルメンテーションの個性」、「テクスチャアの個性」、「美学の個性」と3つの個性をあげている。その中で、「武満の音楽は、人間感情の最もよい意味においてロマンティックであるが、その感情はいつも人間的体験の限度内にある、彼は叙事詩的な効果を求めようと努めない」「彼の音楽は、意気銷沈のあまり狂気となった時代において、正気を代表している」と。
◆ 『武満徹・音楽創造への旅』 立花隆、文藝春秋、2016/2