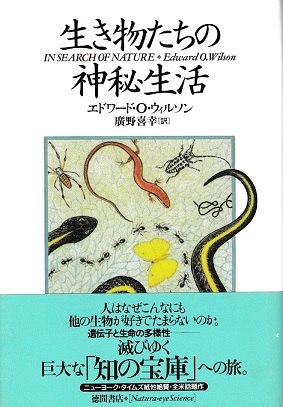
この本は古本屋店頭のワゴンに転がっていた。なんとなくタイトルに惹かれたのだ。寡聞にして著者のウィルソンについてはまったく知らなかった。アメリカの高名な生物学者で、アリの社会的生活などの研究で知られる。著作もかなりある。ピュリツァー賞を二度受賞したとのこと。本書には1975年から1993年にかけて発表したエッセイが収められている。多様性についての言及や、最終章での警告は、あの福島第一原発事故を思い出させる。
著者ウィルソンはアメリカ南部で生まれ野原を飛び回って育った。少年時代のニックネームは「スネーク」だったそうだ。それだけ、ヘビの捕獲に情熱を傾けていたということ。そこには40種という多くのヘビが生息しており、そのすべてを捕らえようと躍起になっていた。
人類は、ヘビを忌避する性質を生まれながらに持っている。ヘビがこのような強い精神的な影響を与えたのはなぜか。おそらく、人類の歴史を通じて数種類のヘビが病気と死をもたらす大きな恐怖だったからだろう。南極大陸を除くすべての大陸に毒ヘビがいるのである。進化の途上においてヘビの襲来といった危険に、日常的に見舞われていると、こうした経験の反復が自然淘汰によって嫌悪として遺伝的にコード化されるのだ。
適応放散という現象がある。生物が進化したなかで、それぞれ特殊化を果たした種が増加してさまざまな生態学的地位を満たしていくこと。多様化と言い換えられるか。たとえば鳥の多様化は非常に進んでいる。捕食する種、腐肉を食べる種、昆虫を食べる種、種子を食べるフィンチ類、……などなど、あげだしたらきりがない。
多様化が進むことによって、そこに生息する種のあいだの生存競争が穏やかになる。限られた生息地に共存できる仲間の種の数も多くなる。つまり、多様化が進めば絶滅の憂き目にあうこともなく、長い時代にわたってより多くの仲間が共存できるようになる。生物の多様性が次から次へと実験を繰り返して新たな形態の生命を誕生させていった結果、ついに行きあたったのが人類なのだ。
人間には大地震や大嵐などの自然災害が起こる可能性や影響を過小評価する傾向がある。この近視眼的な性質にはそれなりの理由があるのだ。長い進化の過程を経て脳が現在の形態へと進化をとげるまで、人間は小規模な狩猟採集集団だった。そこでの一生は危険に満ちた短いものであった。だから、何にもまして重要なのはごく短い未来に対して細心の注意を払い、子どもを残すことだった。
数世紀に一度しか起こらないような大災害は忘却の彼方へとおいやられ、神話へと姿を変えていった。そのため、現代でも人間の心は依然として、たかだか数十年くらいの時間に安住してしまい、1〜2世代を超える期間にまでは配慮が行き届かない。かつては、短期的思考傾向を備えた個体の方が、そうでない個体よりも長命で多くの子供を残すことができたのだろう。未来を考慮することは、自然淘汰を生き延びる上で常に分が悪く作用したのである。
人類は自然界に多くを依存している生物種のひとつにすぎない。知能がどれほど驚嘆に値し、またわれわれがいかに勇猛果敢な精神の持ち主であるにせよ、自然環境の制約から人類を解き放ってくれるほどのものではない。なるほど人類はこれまでいろいろな問題を解決してきた。しかし、些細な問題をあれこれ解決できたぐらいで、自信過剰になってはならない。
◆ 『生き物たちの神秘生活』 エドワード・O・ウィルソン/廣野喜幸訳、徳間書店、1999/1