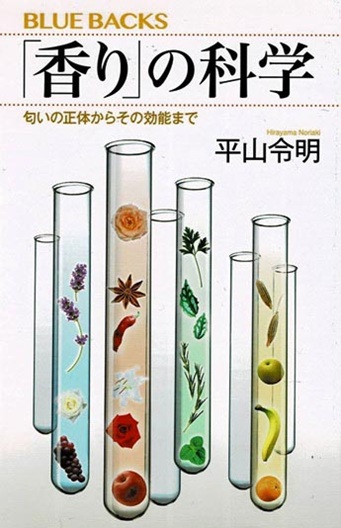
嗅覚(きゅうかく)の特異性を表す言葉に「プルースト効果」と言われるものがある。フランスの小説家マルセルプルーストの著作『失われた時を求めて』には次のような場面がある。主人公がマドレーヌを紅茶に浸した時に、その「香り」が一瞬にして時空を越えて主人公を幼年時代に引き戻すことになった。そして家族と共に夏のバカンスを過ごした田舎町の情景がよみがえった。
嗅覚情報は、原始的な脳の部分で感知される。大脳で情報が解析されることはない。私達の意識に関係なく、「匂い」に対処する活動がすでにからだの中で起こる。したがって、匂いを嗅いだ瞬間に、ある種の感情がどっと湧いて、嗅覚独特の反応がおこる。プルースト効果はまさにその例だ。嗅覚に基づく反応が本来的に生物にとってとても大事で急を要することが多いため、このような仕組みができたと考えられる。
五感のうち、味覚と嗅覚は科学感覚と言われる。感覚が化学物質の種類や濃度によって決まるからだ。水中に生まれた生物にとって、周囲の化学的環境は生命活動を維持していくうえで重要であった。化学物質を認識するメカニズムは最も原始的である。霊長類は哺乳類のなかで唯一、色覚をもつ。この優れた感覚を獲得したために人間は化学感覚に頼る必要がなくなり、進化の過程で嗅覚が生存を決定する重要な感覚でなくなっていった。
「匂い」は細胞に埋め込まれたセンサーが感じる。GPCRという嗅覚受容体タンパク質が匂いを感じるセンサーだ。鼻の奥の上側に、嗅覚細胞が約1000万個ある。嗅覚細胞の間には、ボーマン腺があり、そこから粘液が分泌され匂い分子が粘液に溶ける。嗅覚細胞からは、複数の小毛が突き出ていて鼻腔側に向いている。この毛の表面に嗅覚受容体が並んでいる。人間は821個の嗅覚受容体を遺伝子を持っているという。
良い香りのほとんどは植物に依存している。例えば、ラベンダーは紫の花だけでなく葉や茎にも香りの成分を含んでいる。植物から、香りの成分をとりだすには、古くから、蒸留酒の製造から始まった、「水蒸気蒸留法」が使われる。これは、複数の液体状の化合物が混じった状態から、純粋な化合物を分離する方法である。
香りの成分を分離するには、ペーパー・クロマトグラフィーという分離技術を使う。「匂いの成分」それぞれが、水への溶解性と紙の繊維への結合の強さが色素分子によって異なる性質を利用している。パターンから成分の違いがわかる。紙の代わりに気体を使って分離する方法――ガス・クロマトグラフィがある。気体としてはヘリウムが用いられる。流出する時間差で分子の種類がわかる。
良い香りは心を慰め、癒やしてくれる。中世ヨーロッパではバラのアロマ精油を傷に塗ると治りが早いことが知られていた。ハーブを用いた民間療法も。香りの分子は直接的に感情や情動活動につながる影響を与える。ラベンダーの香りが交感神経の活動を抑え食欲増進させる。グレープルーツの匂いを嗅ぐと、多くの人は新鮮で活動的な気分になる。
◆『「香り」の科学 匂いの正体からその効能まで』平山令明、ブルーバックス、2017/6