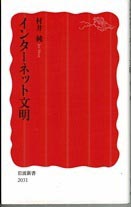
著者は、インターネット黎明期からの日本のオピニオン・リーダーである。現在、当時理想としていた「すべての人のためのインターネット」がほぼ実現したという。本書では、研究活動から現在までを振り返り、改めて「インターネット文明」として展望している。
インターネットの母体となる、パケット交換のネットワークARPNET(アーパーネット)が開発されたのは1969年だ。ウェブはスイスのCERN(ヨ ーロッパ原子核研究機構)で研究者の情報共有ツールとして開発された。1989年だ。1995年にはマイクロソフトのWindows95が満を持して発売された。同年、阪神淡路大震災が勃発したのだ。2011年には東日本大震災が起きる。インターネットは被災地の活動を支える救命ツールとなった。大震災によって、日本人は世界のどの国よりも切実にインターネットがライフラインとして、命を守るためにいちばん大事なインフラだと認識したのだった。
日本はインターネットの黎明期で重要な役割を果たしてきた。1990年代初頭には、まだインフラの環境が不十分であり、とくにIPアドレスの枯渇が大きな問題であった。解決策としてインターネットのアドレス空間を広げるためのコアの開発を日本は担った。もうひとつの貢献は国際言語化の実現だ。サイバー空間で自国の文化を守るためには、自国言語で表現できることがどうしても必要だろう。現在、ウェブブラウザは、ほとんどの言語を扱える。日本語に加えて中国語や韓国語、アラビア語等々。アルファベット以外の文字利用の必要性を訴えて、各国のエンジニアと打ち合わせを重ね、多言語機能の実装という、ややこしくも大きな役割を日本は果たした。
インターネットにおいて日本が産業競争力を落とす残念なキッカケとなったのは、NTTが次世代通信網を開発する際に、アメリカの通信機器大手シスコシステムズの技術を全面的に採用したことだろう。日本の電電ファミリー(NEC、富士通、沖電気など)には、世界レベルの技術力が不足していた。インターネット機器に切り替わるタイミングで、アメリカ企業の独占的な参入を許してしまった。
これからの日本のDXはどうあるべきか。国のIT戦略を見直そうとの機運の高まりから、ワーキンググループが設置され、2019年にはデジタル庁が発足した。著者が強く主張したのは、他の役所にメッセージを伝えられる役所にする、ということ。さらに、民間の力が活躍できる環境にしようということだった。霞ヶ関では、技術のわかる人材を採用していなかったし、科学技術を勉強しなくても出世できた。さらに、2年で異動するとは!デジタル庁は本来、数千人規模が必要と思われたが、現実には300人からのスタートだった。
中国は世界最大のインターネット大国である。この人口数が価値を持つのはAI開発においてだろう。中国のインターネットは、オープンなものから、政府の政策を実現するためのツールに変わって来ている。国内の監視を強化するために、グレートファイアウォールという通信の障壁を設けてインターネットのミニチュア模型をつくっている。その箱庭の中で中国人は生きているのだ。
インターネットという基盤上で日本の世界への貢献が求められる。これからが本当の力の見せ所だろう。日本のインターネット普及率は90%前後と高い。かなり高性能のインターネットを使っていて、ほとんどの国民が一定の水準の教育を受けている。生活レベルの共有感が強いこのような環境からはクオリティの高いデータが収集できるだろう。デジタルデータを基本とする日本のマーケットはデータの質量ともに魅力のあるもののはずだ。
日本のメーカーには要素技術の強みがある。個別の技術やアイデアを磨き上げてユニークなものをつくるにに長けているという。この特質は人にやさしいコンセプトにおいて発揮されやすい。「ドコモのらくらくホン」がその一例だ。高齢者が使いやすいように文字やボタンを大きくしている。弱者に優しく、誰も取り残さない、という日本らしさを生んできた。
著者は、日本の立ち位置として、「周回遅れの先頭ランナー」という言葉を挙げる。先頭のランナーは一周先を走っているかもしれない。たとえ周回遅れであってもいちばん大きな集団を牽引するポジションで走っていれば、多くのランナー達によい影響を与えることができる。世界に先駆けて何かをやるのは苦手かもしれないけれど、気づいたら、ボリュームゾーンの先頭を走っている。それが日本らしいやり方ではないかと。
グローバルなサイバー空間は過去のものとなり、国ごとに切り離されたローカルなインターネットになるかもしれない。そのとき指針となるのが、インターネットにとっては「生命と地球のために」という視点だ。
◆ 『インターネット文明』 村井純、岩波新書、2024/9