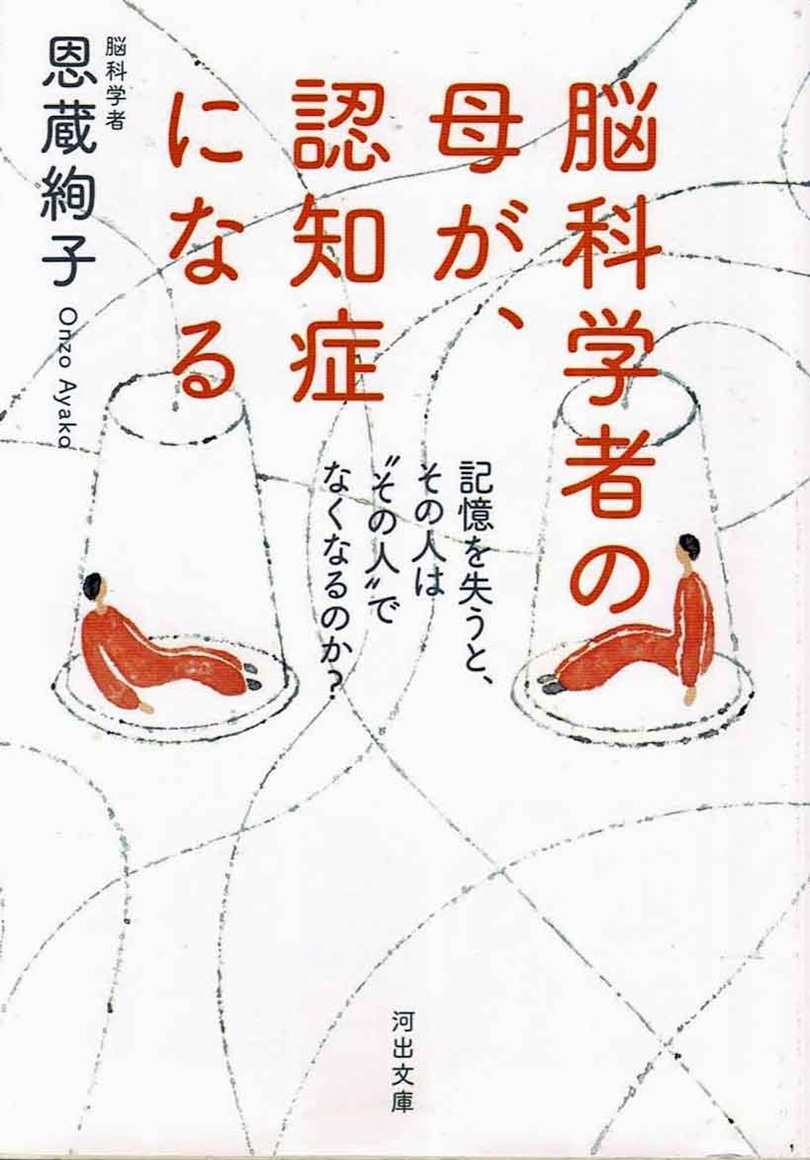
母親が65歳でアルツハイマー型認知症と診断された。活発で社交的な人だった。趣味もいっぱい持っていた。そんな人がアルツハイマーになるのだろうか。誰でも年をとれば認知症になる可能性があるという。85歳以上では2人に1人がアルツハイマー型認知症だというデータがある。異常なタンパク質が脳に蓄積し発症するのだ。記憶中枢の「海馬」に異常が起きると、新しい情報が覚えられなくなってしまう。
本書は、母の発病後の2年半にわたり、脳科学者である著者が、母との日常生活を共にした記録である。著者の観察は鋭い、認知症になっても「その人らしさ」は残っているという。少なくとも、幸せを感じる能力が残っている。簡単なことでいいから自分が主体性を感じられる場所、小さなことでいいから人の役に立つことができて、人から認めてもらえる場所ならそこがすきになるだろう。母なりにたくさんのことを感じて、考えて、学んで生きているのだ。歌が好きなのは変わらないし、これからも、新しいことを覚えることができるだろう。
人間の記憶は短期記憶と長期記憶に分類される。短期記憶は数秒だけ前頭葉に保持されるものである。長期記憶は大脳皮質にしっかり保持されるもので、宣言的記憶と非宣言的記憶に分けられる。
◇宣言的記憶:言葉で書かれる記憶。個人的エピソードの記録など(あの時、あの場所でこんなことがあったな)。海馬は、宣言的記憶を作ったり、思い出したりするために働く。
◇非宣言的記憶:長期間保持されて、言語化されていない記憶だ。自転車の乗り方とか料理とか。
認知症は非常にゆっくりと進行する。アルツハイマー型認知症の初期には、「海馬」の萎縮が起こる。海馬は、貯蔵庫ではないが、記憶において重要な役割をもった組織である。今ここで起こっていること(エピソード)を、大脳皮質に「長期記憶」として蓄える形に、海馬が変換するのだ。海馬が傷つくと、既に蓄えられていた記憶は消えないが、新しいことを記憶として大脳へ定着できなくなる。
アルツハイマー型認知症では、一切のすべての記憶がダメになってしまうわけではない。新しいエピソードを記憶できないとか、適切な単語がうまく思い出せないといった症状につながる。非宣言的記憶には影響を受けないため、自転車の乗り方、スキーの滑り方、家までの帰り方などには問題がない。非宣言的記憶は大脳基底核や小脳が処理している。
現在、アルツハイマー型認知症を根本的に治療する薬はない。いまの薬は、神経伝達物質の働きに作用して脳のネットワークの情報伝達効率に作用するものだ。治療法として奨励されるのは、運動療法、音楽療法、回想療法など。運動には、アルツハイマー病の進行を和らげる効果がある。音楽療法は、不安や鬱、無気力など感情的な問題に対しては有効である。回想療法も思い出を語り合い、他人とコミュニケーションをとることで、孤独感を減らす効果がある。
アルツハイマー型認知症を発病しても、「できること」は残っている。記憶を補えば、できることは増えるだろう。
◇野菜を切る能力など一つ一つの料理能力は残っていた。料理の時間をもうけて、週に2回は、一緒に夕飯をつくるようになった
◇自信があるものについては,極めて自然に進む。自主的に動くのを待つこと◇過去と現在とを混ぜて話す。昔の記憶の中は安心の場所なのだ
◇人は自己が脅かされると保守化する。アルツハイマーでは忘れることが増えて失敗するケースが増える。自尊心がどうしてもきづ付く。自尊心をなんとか守ろうとして、新しいもの、知らないもの、自分と違うものを、排除しようとするのだろう
◇妄想が起こる。アルツハイマーでは最近の出来事の記憶は頼りにならない。自分以外の誰かが、何かしたのではないかと推測し他人を疑ってしまう
◇顔を見ても誰だかわからないし、親しみさえわかない、という状態になることがある。本人や家族が恐れていることの一つだ。脳の萎縮が海馬に留まらず、大脳皮質まで大きく及んだのだろう
◆ 『脳科学者の母が、 認知症になる 記憶を失うと、その人は"その人"でなくなるのか?』 恩蔵絢子、河出書房新社、2021/12